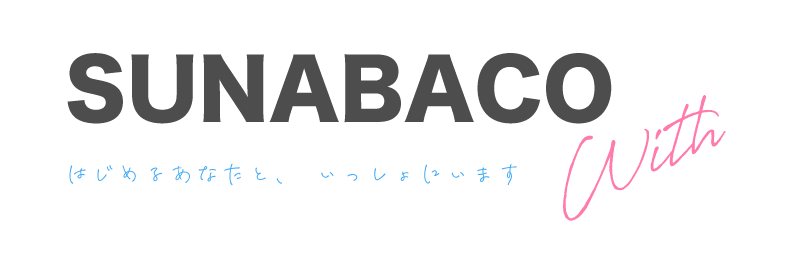(注)このフローはあくまで一例です!
読書、学習、執筆のワークフロー
読書をするのはいいのですが、読書をしてしばらくすると、読んだ気はするが内容を全く思い出せない、ということがみなさんも一度は経験したことがあると思います
それでは知識として自分の中で体系化できてないし、言語化もできていない。つまり、知識が広がっていないのと等しいのではないかと思うようになりました。
その内容を何も覚えていない問題を解決すべき3つのステップを今日は紹介します
ステップ1:読む
ただ読むだけでなくメモを取る事を心がけましょう。余白にめちゃくちゃ書き込みます。線をひいたり、付箋を貼るのはもちろんのこと、余白に自分の考えや他から得た知識を書き記して、自分の知識として体系化していきます。加えて人に説明ができると更に良いでしょう
また、読み終わったら、チェックした重要な文章をiPhoneのメモ帳に全部写経して、常日頃見返すようにしてます。
そして、そこから得た新しい考えは、SNSに投げたり、記事にまとめたりしております。自分の知識として体系化することが重要だと気がついたのです。
Google ChromeにはLinerという強調機能もあるので使ってみるのも良いでしょう。
ステップ2:体系化&言語化
最近、Amazon、Apple、GoodReadsなどの複数のプラットフォームと統合するReadwiseというサービスもあります。外界から得た知識を、一つにまとめ体系化することを意識しています。
形はなんでもいいのですが、人の知識をそのままで終わらせるのではなく、自分の知識として落とし込めるように、体系化と言語化は絶対に必須ですし、その上で実践をして自分の新たなやり方を見つけ、知識に厚みを持たせるのです。
ステップ3:吐き出す
記憶定着率が一番高い学習方法は、人に教えるということです。
人に教える機会は、インターネットにいくらでも溢れています。
一例としてブログを書く、SNSに投稿をする。
自分が得た外界の知識を内在化し、体系化と言語化ができ、その上で自分の考えを載せれたなら、忘れないうちに世界のどこかに書き記しておくのです。それが、いつか誰かの役に立つかもしれませんし、間違いなく自分の知識のアップデートには役立ちます。それを読んだCEOから仕事が舞い込んで来るかもしれません。
まとめ
本を読む事を一つとっても様々な方法があるように何かをする上でいろいろな角度から試すことが大切です!自己流のフローを見つけられると良いですね!是非この記事のフローも試してみてください