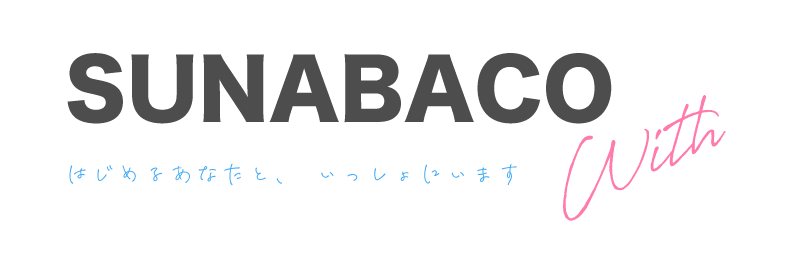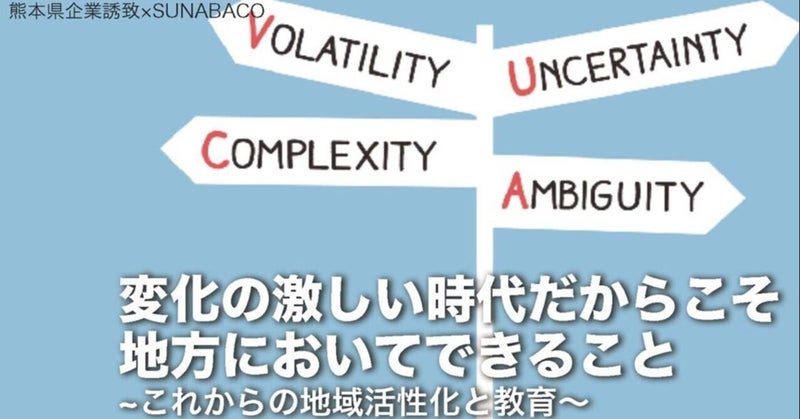2021年8月25日(水)に熊本県天草市から、”地域活性化と教育をテーマ”に
スタディサプリ教育AI研究所の小宮山利恵子氏を講師に招いて講演会と馬場昭治天草市長をゲストに迎えたトークセッションが開催されました。
2020年2021年と,これまでの価値観が問われる変化の年でまさに激動の時代を迎え、
教育分野も大きな影響を受けました。
変化の激しい時代において、地方活性化と教育になぜ注目が集まるのか。教育者だけでなく、
保護者や経営者の方にもオススメの内容になっています。
▼イベントアーカイブはこちら▼
登壇者・ゲスト紹介
小宮山利恵子 氏
1977年東京都生まれ
ゲストスピーカー
早稲田大学 大学院修了。国会議員秘書になるが、ひとり親家庭で育った環境から「すべての子どもたちに教育の機会を」という想いを胸に、教育領域に従事していくと決心する。
議員秘書退職後、株式会社ベネッセコーポレーションの福武總一郎会長(当時)の秘書の職を得る。「教育とは何か」「教育事業とは何か」について学ぶ。その後、グリー株式会社に入社。副業で「東洋経済オンライン」ライターとして教育とテクノロジーについて取材中に株式会社リクルートホールディングスで、オンライン教育アプリ「スタディサプリ」を立ち上げた山口文洋社長(当時)に出会う。「スタディサプリ」のビジョンとミッションに共感し、2015年入社。同年12月より現職。
2019年度より東京学芸大学 大学院准教授を兼務。超党派国会議員連盟「教育における情報通信(ICT)の利活用促進を目指す議員連盟」有識者アドバイザー。経団EdTech戦略検討委員会座長

馬場 昭治 氏
1968年熊本県生まれ
昭和43年11月2日生まれ、52歳。天草市東浜町で育つ。
本渡南小(入学)・旧志柿小(卒業)・旧亀川中・済々黌高校・熊本大学教育学部卒業。衆議院議員公設第一秘書などの職歴を経て、平成11年に天草に戻り家業を継ぐ。令和3年2月21日より天草市長に就任。

1977年福岡県生まれ
シリアルアントレプレナー
アクセラレーター
UXデザイナー
テクノロジストとして数々の
スマートシティ、シビックテックなど先進プロジェクトをリード。
日本最大級のプログラミングスクールSUNABACO代表としてリカレント教育、次世代の教育に関わる。

2020年。かつてない大変革が。
小宮山氏:そもそも2020年はコロナが始まる前から、プログラミング必修化や英語
教育の強化など大改革の年になるといわれていました。
そこにコロナ流行が重なり様々な事をやらなければならなくなりました。
コロナの流行により、1人に1台、パソコンを配るGIGAスクール構想が3,4年前倒しとなったといいます。
GIGAスクール構想は、コロナ流行以前である2019年から、5年間かけて整備する予定だったとのことですが、そもそもなぜこの構想にたどり着いたのでしょうか。
そこには世界の動きと切り取っても切り離せない、とある事情が背景にあったのだそうです。
テクノロジーをめぐる世界の動き。 AIに仕事が奪われる?
未来学者のレイ・カーツワイルは、2045年にシンギュラリティが来ると予測しています。
シンギュラリティとは、簡単にいうとAIが人間の脳を超える事です。
シンギュラリティが私たちの生活に影響を与えることの1つに、「仕事」が挙げられると小宮山氏は述べます。
小宮山氏:「全ての仕事を、AIにとって代わられるのではないか?」とよく質問されます。ですが、私は取って代わられないと考えます。
ただし、一部の仕事は例外です。創造力もいらなくて、かつ共感力も必要ないものについては、今後AIに取って代わられます。
講演の中で、「学校の先生の仕事はAIに取って代わられないが、役割が変わる」 と小宮山氏は述べます。
共感力が必要だけれども、創造力が必要ないものに関しては代わりにAIが行うようになるそうです。
例えば、スタディサプリの学習においても、それぞれのコンテンツのなかではAIが使用されているものの、それを操作したり、使ったりするのは先生の役割として必要だと、小宮山氏は述べています。
そして、先生が必要とされ、AIが置き換わることのできないことのもう1つが、「探究型学習」です。
文部科学省の定める新しい学習要項では、主体的・対話的で深い学び”の視点からの授業改善を目指しています。まさに学校の先生は、創造力と共感力 両方が求められる仕事になっていると感じました。
小宮山氏:答えのない問題に取り組むという事が、非常に重要になってきています。
成長社会は答えがありました。しかし今は答えがない問題が山積みになっています。
21世紀型スキルと言われる、“論理力 創造力 回復力 協働力”によって評価軸が変化してきています。
早く正確に大量なものを作ることから、正解のない社会を生き抜くためにはどうしていけば良いのかという様に評価軸が変化しており、学校教育でも同様の事が言えます。
海外教育現場の取り組み。テストがない公立高校?
小宮山氏は西海岸サンディエゴに位置する、アメリカで1番有名な高校、High Tech Highを学校教育における評価軸の変化の例に挙げます。
High Tech Highには全米から多くの講師が視察に訪れるといいます。
それはなぜなのでしょう。
全米から講師が視察に来る理由
❶テストの代わりに探究型学習(文化祭)で評価
❷地域のばらつきがでないよう抽選で入学する生徒を選ぶ
❸96%の大学進学率
実はこの学校は公立高校です。そのため、経済的に裕福でなく、ランチ補助を受ける生徒さえいます。 その割合なんと42パーセント。
しかし、そのような状況の生徒もいる中で、96パーセントの生徒が大学に進学しているのです。
そして驚くことに、この学校では、テストがありません。
それが、多くの講師が視察に訪れる主な理由になっているといいます。
小宮山氏も実際にこの高校を訪れ、探究型学習の雰囲気を肌で感じたそうです。
まず、日本では1対35や、1対40の授業スタイルが一般的ですが、High Tech Highでは一人一台のコンピューターが配られており、習熟度別にそれぞれ学習を進めていくのだそうです。
では、テストがない中で、どのように生徒を評価するのでしょうか。
それが、文化祭です。
例えば、劇をやりたい生徒はチームメンバーを募って、劇を作るプロジェクトに参加します。
例えばプログラムで何かをしたい生徒は手をあげて、仲間を募って取り組みます。
このように、何かを制作したい生徒は、まず手を挙げ、仲間を募って文化祭に向けて取り組む活動をするとか。
生徒は自ら積極的に学び、まさに「探究型学習」を行うのだと、小宮山氏は述べています。
五感を使った学びの重要性。
小宮山氏:私はテクノロジーと教育を専門としていますが、それらを追求するほど、
アナログやリアルといった五感を使う学びの重要性が痛いほどわかる様になりました。
テクノロジーが発展し始めた当初は、テクノロジーで全て解決できると思っていました。しかしこの4、5年間で明らかに違うと気が付きました。
小宮山氏は、テクノロジー教育の最先端であるエストニアやフィンランドの学校を訪問した際に、授業でテクノロジーに触れる時間と、そうで無い時間のバランスについて質問されたのだそうです。
すると、意外な答えが返ってきたそうです。
訪問先の講師:45分の授業をまるまるテクノロジーに使っているわけでなく、五感を使った手芸や体育などの授業時間を大幅に増やしています。
なぜならテクノロジーは、表現のツールであり道具でしかありません。その表現の基礎となっているクリエイティビティと想像力は五感を使った学びでしか育てられません。
地方だって負けていない。
小宮山氏は、東京のような都市は地方と比べると人口が多く、得る情報量が多いのが事実であると述べる一方で、このように続けます。
小宮山氏:地方には教育資源が沢山あることに加え、かつ地方の方がアドバンテージが大きいと思っています。
コロナが始まる前に毎月の様に訪れていた、宮崎県の児湯郡、新富町では少し歩くとライチ畑、茶畑、ウナギの養殖所や陶芸を作る場所まで行けます。
しかし、東京のような都市では身近でこのような体験が出来ず、消費者という立場でしかありません。
一方で、地方だと生産者の視点も持つことができます。かつ消費者の視点も持つ事が可能なので、これは地方にしかできないことであり、まさに五感を使った体験と言えます。このような五感を使った体験から新たなアイデアを作ることができます。
地域活性化×教育
高校魅力化プロジェクトの公設塾
小宮山氏は、今回の講演会のテーマである地域活性化と教育 について、
関係人口を増やすために教育に重きを置く自治体を例にあげて説明されました。
小宮山氏:島根県隠岐の島海士町は、人口2,000人くらいしかいません。その町には隠岐島前高校という公立の学校があるのですが、
人口減によって、廃校になりそうでした。
高校が廃校になると若い人口が本州や都市に流れる為、その地域が衰えます。そこで、高校が廃校になることを防ぐ為に、対策を取る必要がある。
そんな中で隠岐島前教育魅力化プロジェクトを進めました。そのプロジェクトの一環で、公営塾と呼ばれる塾を島根県の隠岐に設けました。
公営塾に通うと、塾に通わなくてもスタディサプリなどのオンライン授業で学習が安価に出来る為、大学受験までカバーできます。
隠岐國学習センター
結果的に、公営塾がある離島などでは生徒が塾に通うために、わざわざ本州まで行く必要がなくなりました。
これらの取り組みの結果、高校への地域内進学率も高まり、子どもたちの地域外流出が止まった。加えて観光客数や年間平均出生数が増え、島全体に活気が戻ったといいます。
(隠岐島前教育魅力化プロジェクトHPより)
この様な取り組みは、いまや隠岐島前だけに留まらず、久米島や広島、北海道など全国にわたるそうです。
オンライン教育時代に親が大事にすべきこと。
“はっきりとした地図はないのでコンパスを持つ必要がある“
続けて小宮山氏は、「親は子どもに選択肢を提示できるが、選択肢の安全性を保証することは出来ない。」といいます。
小宮山氏:私は会社に在籍していますが、「会社は絶対潰れないから大丈夫」と自分の子どもに言えません。少し前まではそれが言えました。
しかし現代は将来がどうなるか分からない社会である、VUCAの時代と言われています。
昔は熟考してから行動に出ることが重要でした。
しかし現代では、石橋を叩いているうちに橋を渡る必要が無くなってしまう可能性があります。
VUCAとは先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態なこと。
従って現代で必要なのは動きながら考える事です。
小宮山氏は、そんなVUCAの時代にどのようなアドバイスを子どもに与えるべきか4つのポイントに分けて説明されました。
この4つのポイントを繰り返すことによって、子どもが困難な時代を生き抜く力をつけることができると述べられました。
❶子どもの存在を認める ❷コンフォートゾーン(日常)を抜ける体験をさせる ❸小さな選択肢を持たせる機会を多く創る ❹自分で選択させる
最後に、小宮山氏は「失敗」についてこのように紹介されました。
動きながら考えると必ず失敗します。
しかし、失敗しても試行錯誤することで積極的に学ぶことができます。失敗を恐れず動きながら考える組織や人だけが究極のパフォーマンスを発揮できるようになるのです。
▼天草市の魅力はこちらの記事にも▼
https://note.com/sunabaco_event/n/n94c759f6c509
編集後記
今回のイベントで感じたのは、動きながら考えることが必要かつ重要であるということです。
加えて、熊本や天草を始めとする地方ならではの五感を使った体験や経験から多くの事を学べ、動きながら考えるためのアイデアが浮かびやすくなると感じました。
実際に天草を訪れて、五感を使った体験をしてみてはどうでしょうか。